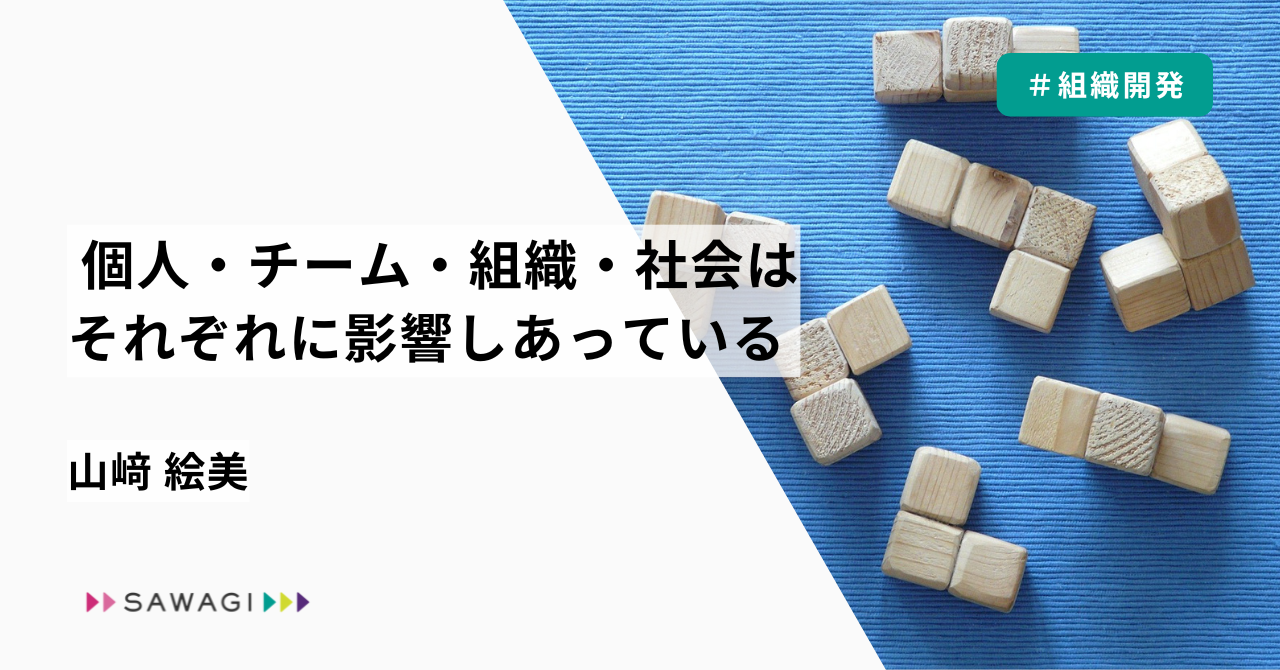私が最初に「人と組織」に興味を持ったきっかけ
私が最初に「人と組織」に興味を持ったきっかけは、今思うと、小学生の頃から関心を持っていたと言えるかもしれません。というのも、家庭という社会の組織の最小単位と考えてみると、母や家庭の中で起こることに非常にアンテナを張り巡らせている子供でした。
今なら、母の言動が決して母個人のものからだけではない、ということが理解できますが、当時は母の矛盾した行動に混乱することも少なくなかったからです。
母はいい意味でも悪い意味でも、社会や家業という外からの影響を非常に受けながら、私たちを育てていたと思います。
例えば、子どもの頃は、台所に入らせてもらえなかったり、お手伝いをすると「そんなことしなくていい」と叱られたり、そうかと思えば「あんたは全然手伝ってくれない!」と怒られたり…。子ども心ながら、「どうしてやっちゃいけないんだろう」とか「どうして言ってることが変わるんだろう」と思っていましたが、それは母が社会の中で求められる「良き妻・良き母」像から遠ざかっていると認知した時に、その苦しさが怒りとなって表現されていたことがわかります。
母としては、「専業主婦で育児に専念するのが望ましい」と考えていたのか、働いている分、子どもに家事を手伝わせる母親になりたくなかったのかもしれません。子どもが台所で手伝おうとすることは、母にとっては働いている自分が否定されたように映ったのかもしれません。でもきっと、母は教育として「お手伝い」の機会を与えたいと考えていたと思います。でも教育という意味づけができないほど、余裕のない日々を過ごしていたのでしょう。
今思えば、母は願いが叶わない社会(家業)へのもどかしさや、自分の理想とする母親像になれない虚しさや葛藤をどこにぶつければいいのかわからなかったのではないかと思います。
このエピソードからもわかるように、「個人の願っていること」と「社会で求められていること」に対して、現状が不一致の場合に葛藤は起こります。
あの時感じた傷みは、「人を理解したい」というパワーと情熱に変換させ、心理学の道へと私を進ませました。これが「人と組織」に興味を持った原点と言えるかもしれません。
問題は個人に原因があるのではなく、個人と社会(システム)の相互作用から起こる
私は大学で福祉学を専攻していました。福祉とは「生きること」「支えること」について学ぶ学問です。ここで社会の見方のベースをつくれたことは、人や組織の支援をする際にとても役に立っています。学生時代は児童虐待に関心を持っていましたが、児童虐待が起こるのは、養育者やその子どもに原因があるのではなく、社会の構造が引き起こしていると捉えることで、養育者を一方的に批判したり、子どもに正しいことを教え諭すようなことを支援としなかったことで、支援の幅を広く持つことができました。
組織変革ファシリテーターとして組織を支援する際も、組織で起こっている問題は誰か特定の人によって引き起こされているのではないと考え、総合的に組織を見立てることを大切にしています。その上で、私たちが得意とするアプローチである「対話」を導入することで、組織が変わる仕掛けを作り出しています。無責任に聞こえるかもしれませんが、他者を変えることはできません。自らが組織の一員としてどんな組織にしたいのか、自分たちが何者であるのか、を定義し、メンバー 一人一人がどんな自分でありたいのかを自覚して行動を変えることが組織を変えることにつながるのです。私たちが変えるのではありません。